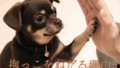🕊️ 前回のお話:第19話「抱っこをねだる理由」
冬の朝六時すぎ。
窓の向こうの空はまだ淡く、部屋の中にはストーブの灯りだけが静かに揺れている。
目覚ましのアラームはとっくに止めたのに、体は布団から離れない。
一週間の疲れが、毛布の重さと一緒に肩にのしかかっているようだった。
妻の「そろそろ起きてね」という声も聞こえている。
返事だけはするけれど、体は動かない。
布団の中で、もう少しだけ、と小さくつぶやく。
そのときだった。
廊下を走る、小さな足音が聞こえた。
タッタッタッタッ——と、迷いのないリズムでこちらに向かってくる。
オペラだけが起こせる朝
次の瞬間、布団の端がふわりと沈んだ。
オペラがベッドに飛び乗ってきたのだ。
その勢いのまま、額と頭のあたりを、前足でわちゃわちゃとかき回していく。
一度わちゃわちゃして、くるりと向きを変えて、少し離れる。
「起きた?」とでも確認するみたいに、こちらの様子をうかがう。
そして、まだ動かないと見るや、再びタッタッと戻ってきて第二波のわちゃわちゃが始まる。
これを二回、三回。
まるで自分なりの“スヌーズ機能”を備えているかのようだった。
妻に起こされても起きられないのに、
オペラの足音と、額の上を行き来する小さな前足には、なぜか逆らえない。
目を開けてしまう。
伸ばした手が、自然とオペラの体を探していた。
妻の声がけと、オペラの突撃。
どちらも、この家の朝には欠かせない。
ただ、オペラが相手だと、僕はなぜか無条件で降伏してしまう。
罪悪感と、静かな信頼
抱き上げると、オペラはすぐにおとなしくなる。
さっきまで猛ダッシュしていたとは思えないほど、すっと腕の中におさまって、
胸のあたりに顔を寄せてくる。
耳を近づけると、小さな鼓動が聞こえた。
朝の冷たい空気の中で、その鼓動だけがやわらかく、はっきりと存在している。
この子は、長い時間の留守番もできるようになった。
電気をつけたままの静かな部屋で、
僕たちが帰ってくるのを、きっとじっと待っている。
そう思うと、胸のどこかがきゅっとする。
一緒にいてあげられない時間の長さを、
抱きしめる腕の重さが、そっと教えてくるようだった。
それでもオペラは、そんな迷いを気にしている様子はない。
ただ、「見つけたよ」というように体を預けてくる。
その信頼の重さに、少しだけ背筋を伸ばしたくなる。
見張られている夜
夜中、ふと目が覚めることがある。
枕元の暗がりで、じっとこちらを見ている気配がするのだ。
目を凝らすと、オペラの瞳がこちらを見ている。
ガン見と言ってもいいくらいの集中力で。
まるで「ちゃんと寝てる?」と確認しているみたいだった。
その視線に気づいて、「どうした?」と声をかけると、
オペラは小さくあくびをして、また丸くなって眠ってしまう。
見張り番の交代を終えたみたいに。
そんな夜のことを思い出しながら、
朝の腕の中で、オペラの体温を確かめる。
留守番の時間も、真夜中のガン見も、
そしてこうして起こしに来てくれる朝も、すべて同じ線の上にある気がした。
いつの間にか、僕の一日は、
この小さな足音とともに始まるようになったのだ。
あとがき
自分ひとりのためだけでは、なかなか起きられない朝がある。
けれど、「誰かのために起きる」理由があると、
体は思っているより素直に動きはじめる。布団のふちに届く小さな足音と、
額の上をわちゃわちゃと駆け回る前足。
そのすべてが、「今日も一緒にいこうよ」という合図のように思えた。オペラに起こされる朝は、
少しだけ、世界に向かって顔を上げやすくなる。