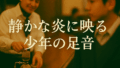🕊️ 前回のお話:第1話「喫茶カトレアで聴いたジャズと、クリームソーダの記憶」
家の中で一番コーヒーの香りがする時間、それは朝だった。
母が黒いラベルの瓶を開けると、カチッと音がして、
「ああ今日も始まるんだな」って思う。
僕の子ども時代の“モーニングコール”は、目覚ましでも鳥の声でもなく、
ネッスルの香りだった。
☕黒い瓶と白い粉のゴールデンコンビ
要約: ネッスルとクリープの登場が、我が家の朝を支配していた。
母はインスタントコーヒーを「ネッスル」と呼んでいた。
当時はそれが普通の呼び方で、「ネスレ」なんて言い方はしてなかった。
(いまは世界共通で“ネスレ”らしいけど、昭和の空気の中では“ネッスル”がしっくりくるのよね。)
瓶のフタを開けて、スプーン一杯すくってカップへ。
そこに白砂糖を二杯、クリープを一杯。
「今日はブラックよ」と言いつつ、僕のカップはなぜか“ほぼミルク”。
甘いミルクコーヒーにトーストをサッと浸して、
口に放り込むのが当時の定番。
いま思えば、朝の味覚も昭和らしい“手早い幸福”だったなぁ。
🍶母のドリップは“見よう見まねの芸術”
要約: 形式じゃなく感覚で淹れる母のコーヒーが、なぜか一番うまかった。
ある日、母がスーパーの実演販売でハンドドリップセットを買ってきた。
「これ、お兄さんが上手に淹れててねぇ」と、うれしそうに話していた。
ところが、家で淹れてみるとペーパーがズレてお湯が横漏れ。
それでも香りはちゃんと美味しかった。
母は「失敗した」と言いながら、
なぜかその失敗作が一番うまい。
たぶん、“味”じゃなく“空気”を淹れていたんだろう。
あのときの御勝手(今で言うリビング)の空気の柔らかさ、いまだに覚えている。
☕僕の初ドリップと小さな反逆
要約: 見よう見まねで挑戦した、少年おぷっぷの“はじめての成功”。
中一のある夜、母の留守中にこっそりドリップした。
見よう見まねの自己流。
お湯の注ぎ方なんて知らないのに、
「母の手首の角度ってこんな感じだったかな」と真似しながら。
結果、なぜかちゃんと美味しくできた。
母に報告すると「ふ〜ん」とだけ。
でも翌朝のコーヒーがいつもより丁寧に淹れられてたのを、
僕はしっかり見てた。
☕味よりも、あの“間”を受け継いで
コーヒーって、味の前に“間”がある。
お湯を注ぐ静かな時間、
立ちのぼる湯気を眺める余白、
その中で心が整う感じ。
母のドリップは、たぶんその“間”の美学だった。
僕の何気ないしぐさや人生においても
その“間”を大切にしている気がする。
💬共感のひとこと
あの頃のネッスルの香り、今も心のどこかで湯気を立ててる。