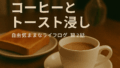🕊️ 前回のお話:第2話「ほぼミルクのコーヒーとトースト浸し — 僕の原点は“ネッスルの朝”」
1980年代の初め。
中学生の僕は、部活よりも喫茶店に通う時間のほうが好きだった。
今思えば、かなりの変わり者だ。
でもあの頃の僕にとって、喫茶店は“静かな避難場所”だった。
炎が揺れ、湯気が昇り、誰も僕を試さない場所。
そこには、大人たちの時間が流れていた。
その空気の中で、僕は少しだけ息をしていた。
☕カツン、コツン ― 自分の足音を聞く場所
要約: 木の床の音とともに、自分の存在を感じた少年の心。
駅前の、凛としてやさしい空気の喫茶店だった。
木の床を歩くと、カツン、コツンと響く音。
その音を聞くたびに、「あ、僕は今ここにいる」って思った。
誰かに名前を呼ばれなくても、足音が僕の居場所を教えてくれる。
小6と中1の頃、学校ではうまく笑えない時期があった。
消えてしまいたいと思ったこともあったけれど、
この店に来て、自分の足音を聞くと不思議と落ち着いた。
“堅い音の中にあたたかさがある”――
それが僕の生きる音だった。
☕アルコールランプの青い炎
要約: サイフォンとの出会い。炎と香りが少年の心を動かす。
カウンターの奥では、
小さな青い炎がゆらゆらと揺れていた。
下のボールでお湯が沸き、
上のボールにコーヒー粉がゆっくりと押し上げられていく。
その透明な管を流れるお湯が、
まるで何かの儀式のように見えた。
ふわっと香りが広がるたびに、胸がキュッと鳴った。
それが「大人の世界」の入口に触れた最初の瞬間だった。
☕マスターの“静かな手”
要約: 技術よりも、沈黙の中にある美しさに惹かれた。
マスターは無口で、笑うことも少なかった。
でも、手だけは優しかった。
木のヘラを静かに動かし、
コーヒーの中で小さな渦を描く。
その動きには、時間のリズムがあった。
何も言わなくても、伝わるものがある。
僕は思った――
この人は“火とも香りとも友達”なんだ、と。
その瞬間、
ああ、自分もいつかこんな“静かな仕事”をしたい、
そう思ったのを今でも覚えている。
☕修行のはじまり
要約: 憧れの背中に一歩近づいた瞬間。
何度も通ううちに、
マスターが僕の顔を覚えてくれた。
ある日、閉店間際にこう言われた。
「見てるだけじゃ、味は覚えられないよ。」
心臓が跳ねた。
「え? ぼ、僕が?」と裏返った声。
マスターはにやりともせず、ただ頷いた。
震える手でアルコールランプに火をつけ、
サイフォンをそっと持ち上げる。
炎がガラスに反射して、
自分の顔が赤く照らされた。
「お湯の温度より、心の温度を落とすな。」
その言葉が胸に染み込んだ。
意味はわからなかったけど、
その響きだけで、何かが変わった気がした。
☕音と香りの中で育った心
コーヒーの香りと、床を踏む足音。
どちらも、あの頃の僕を確かに生かしてくれた。
マスターの沈黙の手。
アルコールランプの青い炎。
その中で、僕は“丁寧に生きる”ということを教わった。
サイフォンの炎がゆらめくたび、
今でも胸の奥で、あのカツン、コツンという音が響く。
――僕が「ここにいる」と教えてくれた音だ。
💬共感のひとこと
誰の言葉でもなく、
自分の足音が「生きてるよ」と言ってくれたあの頃。