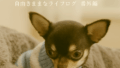🕊️ 前回のお話:第14話「白い息の向こうで」
夜が静かに降りていた。
机の上には、書きかけのノートと、冷めかけたコーヒー。
ストーブの小さな炎が、壁に淡い影をつくっている。
その光の中で、ペン先がかすかに動いた。
言葉が生まれる音が、冬の空気の中にほどけていく。
灯をともす手
ペンが紙をなぞるたび、
時間が静かに息をしていた。
インクの匂いがかすかに漂い、
ページの端に触れる指先が、温度を覚えていく。
書くことは、言葉を残すことではなく、
その瞬間を生きること。
何かを記すたびに、見えない灯がひとつ、
心の奥にともっていく。
静かな証
ページをめくる音が小さく響く。
夜の深さをゆっくりと刻んでいく。
過ぎた日々の文字が、静かに並び、
そのひとつひとつが、確かにここに生きていた証になる。
言葉は誰かに読まれなくてもいい。
ノートの中にあるのは、
“続いてきた日々の呼吸”そのものだから。
それを見つめることが、今を照らす行為になる。
オペラの寝息
足元で、オペラが丸くなって眠っている。
その寝息が、部屋の静けさをやわらかく包む。
ストーブの光に照らされた毛並みが、
ほのかに光を返していた。
ページを閉じる。
インクの香りが、まだ空気の中に残っている。
それは、今日という一日が確かにあった証。
灯は静かに息づきながら、
また新しい朝へとつながっていく。
あとがき
言葉は、風のように過ぎていく。
けれど、書くという行為は、
その風の中に小さな灯をともすこと。ページをめくるたびに思う。
この灯が、どんな夜にも、
そっと自分を照らしてくれますように。